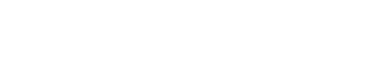- TOP
- 治療について
- 漢方・鍼灸治療

漢方・鍼灸しんきゅう治療
漢方や鍼灸を取り入れることで、
西洋医学のみでは得られなかった治療効果が期待できます。
長期間患っている病気には特に有効で、西洋医学と中医学の治療を併用することで、
治るまでの時間を短縮したり、お薬の副作用を軽減したり、
西洋薬の継続使用によって起こる弊害を避けるなどのメリットがあります。
基本的な考え方
漢方・鍼灸を用いた治療の基礎にあるのは、中国医学すなわち中医学(※)です。この医学理論では、全ての病気は原因を問わずに、『身体の持っている自然治癒力 vs 身体に侵入してやっつけようとする勢力』の対決と考えます。
そして、漢方・鍼灸は身体のアンバランスを整えて自然治癒力をアップさせ、侵入者を打ち負かす戦略です。従って、西洋医学では『治療法のみつからない病気』『原因がわからない病気』『手の施しようのない末期のがん』に対しても、漢方・鍼灸療法をご提案できます。
※…WHO(世界保健機構)では中医学は中国の伝統医学のこと、東洋医学は日本の”漢方”、すなわち日本の伝統医学のこととして区別しています。漢方は、中医学の一部が日本国内で独自の変化を遂げたものであり、漢方=中医学ではありません。
病気のとらえ方 ~西洋薬との違い〜
また、高齢動物は複数の慢性病を患うことが多いのですが、西洋医学ではその病気の部位ひとつひとつを独立的にとらえ、其々に適応する薬を処方します。従って、ときには1頭の犬に10種類以上の薬を投与する状態になります。
一方、漢方・鍼灸療法では整体観念という考え方で、動物の身体をひとつの有機的な総合体と捉え、身体の各部分は相互に影響を及ぼし合っていると考えます。従って、処方する漢方薬は包括的なものとなり、ひとつの処方で複数の病気が好転することもよく見かけます。漢方・鍼灸療法は、動物個々の体質に応じたオーダーメイドな治療なのです。

副作用が起こりにくい
慢性病で長期に渡って同じ西洋薬物を使うと副作用も発現しやすいのですが、漢方薬ではこれも回避できます(※下記FAQを参照ください)。漢方療法では、病気は静止した状態ではなく常に状態・状況が変化していると捉え、同じ病気でも経過とともに処方を変えるからです。
未然に病気を防ぐ
漢方・鍼灸療法には未病を治すという概念、すなわち病気を未然に防ぐことにも積極的です。飼っている動物が健康に過ごせるような予防医学も可能となります。この漢方・鍼灸療法については、獣医大学では学べません。漢方治療をする獣医師は、獣医大学とは別に、人間の中医学か東洋医学の専門学校に通うか独学で勉強することになります。
漢方・鍼灸治療のよくある質問
-
- Q1西洋医学と何がどう違うの?
-
西洋医学では、病気に対して原因と症状に焦点を絞って治療方針を組み立てることが多いのですが、中医学(漢方治療)ではどこかに不調が起こった場合、関連するいくつかの臓器にも問題があると考えます。つまり病気を『身体のバランスが悪くなった』と捉えます。従って治療とはそのバランスを整えて元の健康な状態に戻すことを指します。
ですから、西洋医学とは診断治療の切り口が全く異なり、病気によって生じる身体全体の不調を総合的に診ますつまり、木個々というよりは森全体を見て、森全体を治すのです。これによってときに漢方薬を使うとひとつの処方で複数の病気が好転したり、主症状以外の症状緩和が見られることも多く経験します。
-
- Q2漢方薬は、自然のものなので副作用が少ない?
-
漢方薬には、西洋薬で起こるような副作用は多くはありません。漢方薬で副作用が現れる原因は主に、適正に使用されなかったことによります。つまり、使った漢方薬が患者の相性に合わなかった場合に発現します。そして多くは投与初期に軽い症状で現れるのがほどんどです。これは漢方薬の原料が天然物だからという理由ではなく、薬の中に調和が有るからだと言われています。
漢方薬は、植物や鉱物、動物など自然界にある天然物を原料にして作られます。これらの原料ひとつひとつを生薬(しょうやく)と呼びますが、漢方薬は複数の生薬の巧妙な組み合わせとバランスで成り立っています。つまり、漢方薬には西洋医学的には何百種類もの化学物質成分が含まれていることになるのですが、これらがまるでオーケストラのように調和して効果を発揮します。単独では毒性・副作用のある成分も、この調和によってその緩和や抑制作用が発現します。
加えて、漢方薬は古代より現在に至るまで使用されている間に、先人たちが毒性や副作用を取り除く加工方法をも体得しています。
-
- Q3西洋薬と漢方薬の違いは?
-
新見正則先生の著書(注1)にありました表現が的確なので拝借いたしますと…蒸留水(H2O)よりもミネラルウォーター、精製塩(NaCl)よりも天然塩、エチルアルコールよりも大吟醸の方が、味わい深く美味しくないですか?ということなのです。西洋薬は蒸留水であり精製塩でありエチルアルコールです。つまり、西洋薬は化学物質の単剤であり、漢方薬はさまざまな成分が様々な量でしかも様々な形態で混合されています。
現在使われている西洋薬の中には、ある漢方薬中に存在する主な化学成分をひとつだけ抽出分離して構造を調べ、化学合成したものがあります。これらの単剤は、確かに効き目はシャープです。ひとつの生薬を取ってみても非常に多種類の生理活性物質が含まれているために、複雑な効果を発揮する漢方薬とは対照的です。
ところで不思議なことに、この西洋薬の単剤には、元の漢方薬の効能は消え去って、別の効果がある薬として活用されているという場合があります。『漢方薬は調和してこそ薬となる』ということなのです。
(注1)新見正則 本当に明日から使える漢方薬 新興医学出版社
-
- Q4漢方薬は、自然のものなので体に負担のかかるものは入っていない?
-
天然物といえども、身体にとって異物は異物、毒物は毒物です。例えば朱砂(しゅしゃ)という生薬は、水銀鉱物であり主成分は硫化水銀HgSです。心を落ち着かせ、皮膚の化膿炎症反応を鎮静化させる効果があります。附子(ぶし)は体が冷えて弱っているときに用いられる生薬ですが、大量に服用すれば死に至る劇薬です。なぜそのような毒物を使うのでしょうか?漢方では「毒をもって毒を制す」という考えがあるのです。そもそも、薬とは毒です。毒で病気という敵をやっつけなくてはいけません。西洋医学でも、癌という敵には抗がん剤という副作用の強い毒薬で立ち向かいます。ただし、漢方薬は上述のように調和があるために、毒性の緩和や抑制効果があるのです。
-
- Q5漢方薬は速効性がない?
-
漢方薬の中には、速効性のものもあります。例えば大出血してショック状態の患者に対して救急処置として与える漢方薬や、インフルエンザに効果がある漢方薬がそれです。
一般的に、西洋医学では主症状に対して薬が処方されるのに対して、漢方治療では、症状が出るその上流にある原因・不調を取り除くことを主眼において薬が処方されます。同じ病気・同じ症状でも、原因は必ずしも皆同じではありませんので。漢方治療では同じ病気でも異なる薬、違う病気でも同じ薬が処方されるということが起こり得ます。
もちろん、漢方薬にも症状を抑えるだけの薬もありますが、その速効性は西洋薬にはかないません。したがって、一般的には西洋薬は早く良く効き、漢方薬は効き目が遅いと感じるのではないでしょうか?ただし、西洋薬の中には、その病気の根本原因を治さないため、薬を止めればまた症状が出るということも少なくありません。
-
- Q6漢方薬は効き目が緩やか?効いているのか良くわからない?
-
漢方薬を使ってみたけれども効かない、効いているのかどうかわからないというときは、2つの原因が考えられます。ひとつめは、(獣)医師の見立てが悪かったということです。(獣)医師は病名ではなく患者の身体全体を良く診て、体質やバランスを把握して処方を出しますが、それが適切ではなかったということです(すみません。)
2つめは、漢方薬中の生薬は、特に植物由来のものが顕著ですが、例えば似て非なる植物が使われていたり、同じ植物であっても生育する土壌・気候・風土・害虫の発生状況などの自然環境により、あるいは生育期間や採取される次期・時間によっても化学物質の組成が異なってしまうため、作成された生薬、ひいては漢方薬が目指すものと異なってしまうからです。このような場合ですが、同じ名前の漢方薬エキス剤が複数の会社から発売されていることがあり、これらは原料調達先や加工、生薬の比率が多少異なる場合がありますので、別の会社のエキス剤を使うと効き目を実感できるということもあります。
また、中医学では病気は静止した状態でなく常に状態・状況が変化していると捉えるので、同じ病気に対して使う漢方薬はどんどん替えていく必要があるにもかかわらず、漫然と同じ処方を続けていると効かないと感じたり副作用が発現したりします。
-
- Q7漢方薬と民間薬の違いは?
-
マムシやドクダミといった民間薬は、生薬1種類で構成されています。一方、漢方薬は生薬の巧妙な組み合わせとバランスで成り立っている調和のある薬です。
-
- Q8漢方薬は液体?錠剤?粉末?
-
本来の漢方薬は、植物や鉱物、動物などを原料として加工し細かく砕き、水で煎じて濾(こ)した液を服用するのが一般的です。しかしこれでは毎日の作業が大変ですので、近代技術によりこの煎じ薬を濃縮して、でんぶん、乳糖などを混合し、粉末や錠剤にしたエキス剤と呼ばれるものがあります。煎じ薬をドリップコーヒーに例えると、エキス剤はフリーズドライのインスタントコーヒーに相応します。ここでまた、インスタントコーヒーよりも豆からいれるドリップコーヒーの方が、香りが豊かで美味しいと思うのと同様に、煎じ薬の方が効き目が良いということはあると思います。また、生薬の量を患者に合わせて微調整できるのも煎じ薬の良い点です。しかし、手軽さ・飲みやすさではエキス剤の方が優れています。病院での処方にかかる時間も、エキス剤ではさほど時間はかかりません。
動物に漢方薬を飲ませるには元来の煎じ薬は不適と考えますので、最初に処方するのは主に錠剤か粉末になった製品です。
-
- Q9どういう病状のときに、漢方・鍼灸療法という選択肢が可能?
-
長期間、副作用の強い西洋薬を飲まざるを得ない慢性疾患、西洋医学では治療法のない末期のがん、原因がわからない病気などの症状改善に、漢方・鍼灸による治療を提案出来ます。中医学的な治療とは、身体のバランスを整えることを指しますので、西洋医学的な病名が無くとも処方が可能なのです。
不治の病、例えば末期のがんになったとき、抗がん剤投与や輸血で頻繁な通院をするのは、飼い主にとっても動物にとっても苦痛なのでは?と感じるときは、漢方・鍼灸療法を選択するのもひとつだと思います。痛みや不安を和らげ、体調を整えて病気の進行を少しでも遅らせ、残りの生活を穏やかに過ごせるかも知れません。痛みが酷い場合には、即効性がある西洋の鎮痛薬を併用することも適切な処置であると考えます。
-
- Q10西洋医学と漢方・鍼灸療法は併用可能?
-
近年、「統合医療」という言葉が使われるようになりましたが、これは西洋医学と補完代替療法や伝統医学である漢方・鍼灸療法などを組み合わせて、病気を多方面からアプローチする療法です。それぞれのメリットを最大限に利用できるこのような療法は、今後積極的に取り入れるべきであると思っております。
漢方療法と西洋医学を併用することに関する分類があります。
1.漢方療法が西洋医学の治療よりも優れているもの→漢方療法を単独で使用
2.西洋医学との併用で両者の効果が増強するもの→両者を併用、さらに西洋薬を減薬できる可能性
3.漢方療法で西洋医学の薬剤の副作用を軽減できるもの→両者を併用
4.西洋医学の薬剤に対する副作用のために西洋医学的治療を行えないもの→漢方療法
5.西洋医学的な治療とほぼ同等な効果が得られ、経済的に安価なもの→漢方療法を使用
安井廣廸 統合医療としての漢方医学の形 第69回総会 特別講演 より
-
- Q11漢方・鍼灸は自己免疫力を上げるの?体質改善するの?
-
漢方・鍼灸による治療効果を平易な言葉でいうと、体質改善ということになります。自己免疫力については、身体のバランスが保たれていればウイルスや細菌、がんなどの敵を打ち負かす力、すなわち免疫力は強くなります。漢方・鍼灸による治療は身体のバランスを整えることにあるので、そういった意味では自己免疫力をあげるのでしょう。
動物の身体は老齢になると、日に日に衰える肉体に心が対応できずにバランスが崩れ、あちこちに問題が発生します。このとき中医学的には『身体全体を調える』治療になりますが、西洋医学的にはその病気の部位ひとつひとつを孤立的にとらえ、対症療法的な薬物を投与する治療となってしまいがちです。従って其々の病気に対して複数の薬物を処方することとなり、ときには10種類以上の薬を投与される状態となります。しかし漢方治療では、整体観念という考え方で人体をひとつの有機的な総合体と捉えます。したがって漢方薬の処方は各病気の総括的なものとなり、ひとつの処方で複数の病気が好転することも起こり得るのです。高齢動物と漢方薬は相性が良いと考えます。
-
- Q12ツボとは何?
-
中医学では、人間も含めた動物の体内には、『気』(正しくは『氣』と書き、『き』と読む、現代用語のエネルギーのようなもの)の流れる通路(経絡,けいらく)があると考えます。しかしこれは、目に見える形のある通路ではありません。この通路には、地下鉄が駅で地表と通じているように、体表との連絡口があり、これを経穴(けいけつ)、ツボと言います。
中医学では身体全体のバランスが崩れたときに病気が発生すると考えるのですが、それはすなわち、経絡内の氣の流れが淀んだり、枯れたりなどの不調が根本原因と考えます。鍼灸は、経穴を刺激することによってこの氣の流れを整え、機能回復をはかる治療法です。
鍼(はり)は、注射で使用するよりもずっと細い針をツボに刺します。とても細いので、多くの場合、痛みはほとんど感じません。全て使い捨ての鍼を使用しております。灸(きゅう)は、乾燥させたヨモギ葉の柔毛を精製して固めたものに火をつけて、火傷しないように皮膚やツボにあてるものです。
-
- Q13鍼灸ってホントに効果があるの?
-
鍼灸の効果については、人間でも動物でも、西洋医学的、近代科学的に研究が進んでいます。例えば、鍼灸で一部の経穴を刺激すると、痛みを和らげるホルモン(内因性オピオイド)が体内で分泌されることが報告されています。また、鍼灸は自律神経に作用して、心臓や胃腸などの臓器の働きを調整することがわかっています。
温灸は単に身体を温めるだけでなく、その独特な香りも効果の一助となっています。ヨモギ葉の柔毛が燃えると、有効成分である精油がその香りとともに嗅覚を刺激し、肺を通って血液中に入り、人間や動物をリラックスさせます。そして、身体を芯から温めて免疫機能、代謝機能などを高めるとされています。
-
- Q14鍼灸はどのような病気に有効なのか?
-
人間も含めた動物の身体は、歳とともに代謝が落ちて血液の流れが悪くなり、結果的に痛みが発生したり病気に罹ったりします。
鍼灸はこの代謝や血液の流れを改善しますので、加齢による病気や症状には顕著な効果を発揮します。高齢でなくとも、長期間病気に罹っていると体力が落ちて、いわゆる虚弱体質になりがちですが、この体質改善にも有効です。また、鍼灸は関節炎や椎間板ヘルニアなどの痛みや麻痺にも有効とされています。最初は集中して施術し、症状に改善がみられたら徐々に間隔をあけて施術することが一般的です。